最前線で働く公務員が、日々どんな思いで働いているのかを深堀る『公務員図鑑』
今回のゲストは、さつま町で事務職として働く下麦大志さんです。
前編では、コロナ禍での働き方や、下麦さんのルーツについて、お話を伺いました。
下麦さんの姿をとおして、普段日の目を見ることが少ないけど必死に働いてる公務員の姿を、少しでも身近に感じてもらえると嬉しいです。
<聞き手=上木寿人(KagoshimaBase取材者)、森満 誠也(KagoshimaBase編集者)>
下麦さんのプロフィール
1980年8月生まれ。
鹿児島県さつま町(旧 宮之城町)出身。
高校までを鹿児島で過ごし、大学進学を機に関東へ。
大学で経済について学んだ後、就職氷河期ど真ん中で、宮之城役場(現 さつま町役場)へ入庁。
税務課や企画課、鹿児島県大阪事務所への出向等を経て、現在の商工観光PR課へ。
役場内外の様々な仲間と共に、移住ドラフト会議やオンライン交流会等、さつま町を盛り上げるべく奮闘中。
いじる側もいじられる側もこなす、マルチプレイヤー。

公務員としての顔
役場内で売ってる温かい弁当

今日はよろしくお願いします!
貴重な昼休みの時間をありがとうございます!
役場内で弁当売ってるおばちゃんたちが優しくて、ほっこりしました。笑

わざわざ来ていただいて、ありがとうございます。
鹿児島市役所でも、弁当売ったりしてませんか?

注文したら持ってきてくれるんですけど、とにかく職員数が多いので、弁当も早い時間に作らないと間に合わないんだと思うんですよね。
だから、弁当は大抵冷たくて。

電子レンジも無いから、いつも冷たいよね。笑

地味に辛いですよね。笑
近くにランチ営業してるお店はたくさんあるんですけど、毎日ランチに出れるほどの経済力が無いので。。

なるほど。笑

下麦さんは、外でランチ食べたりもしますか?

いやー、コロナ以降はほとんど注文したものを役場に持ってきてもらってますね。
ありがたいですよ、ほんとに。

新卒で宮之城町役場へ

下麦さんって、新卒で公務員になったんですっけ?

ですです。
大学を卒業した後、平成15年4月に(旧)宮之城町役場に入りました。
平成17年3月に宮之城町、鶴田町、薩摩町が合併して、さつま町になったんですよ。

入庁してすぐ合併したわけですね。
今までどんな部署で働いてこられたんですか?

新規採用から5年間は、税務課に配属されてましたね。
そのあとは、環境課で3年、企画課で2年。
そこから、外で勉強してこいと言われて、鹿児島県大阪事務所に2年間出向してました。

鹿児島県大阪事務所への出向

なるほど!
鹿児島県大阪事務所ではどんな仕事を?

業務としては、1年目が『企業誘致』に関することをメインでやってて。
2年目は『観光』に関すること、中でも、関西方面からの教育旅行(修学旅行)に関することや明治維新150周年カウントダウンに関連した「鹿児島ゆかりの地ツアーin関西」を担当しました。


面白そうな業務…‼笑
その頃って、明治維新150年で盛り上げようとしてましたもんね。

個人的にも歴史が好きでして。。笑
関西には、薩摩藩にゆかりのある場所がたくさんあるんですよ。

へぇ!
全然知らなかったです。
具体的には、どんなことを?

普段オープンになっていない京都のお寺に交渉しに行ったことがあって。
そのお寺にOKをいただき、ツアーで訪問し、参加していただいたお客様に感謝された時はうれしかったです。
良い思い出の一部ですね。

最高ですね…‼
企業誘致に関してはどんなことを?

関西から鹿児島県内への企業進出や、誘致企業のフォローなどを経験をさせていただきましたね。

なるほど。

それまで、公務員として“営業・セールス”という分野に縁が無かったのですが、大阪での2年間で『自治体をどう売り込むか』っていうところをすごく考えさせられましたね。
勉強させていただいたのに、まださつま町で結果を出せていないのが悔しいところですが。。
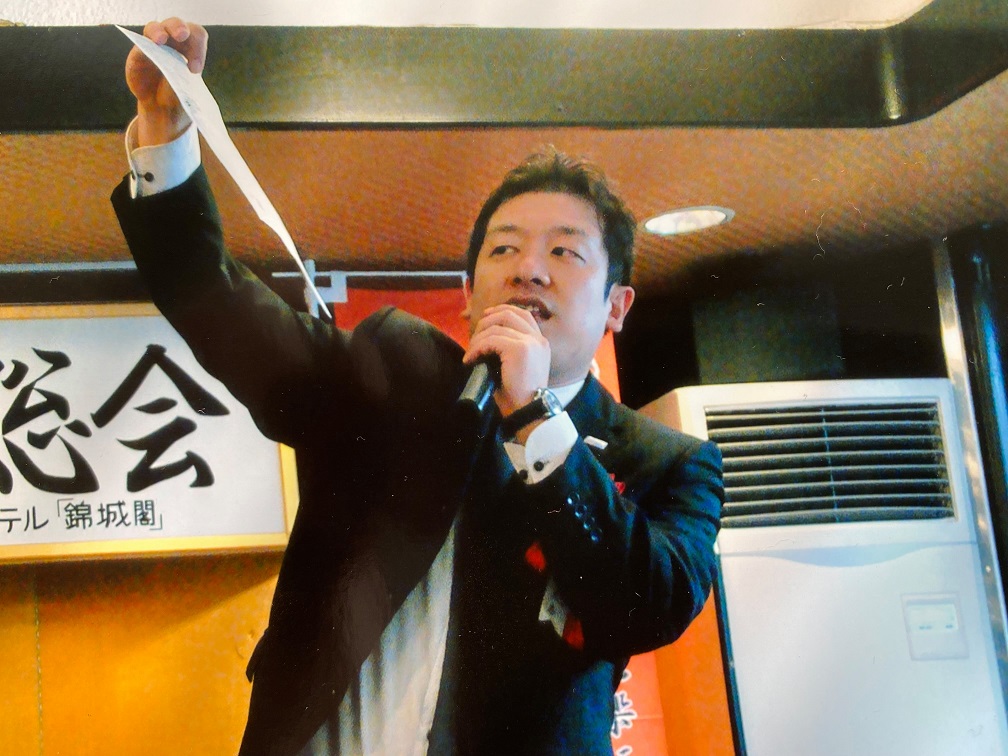
希望調査と人事異動

濃厚な大阪での2年間を経験した後、さつま町役場に帰ってきたわけですね?

そうです。
平成27年にさつま町へ戻ってきてからは、ずっと商工観光PR課で働いてます。
ここが結構長くて、、もう7年目になりますね。笑

ほぼ専属みたいな感じですね。笑

まぁ、大阪まで2年間も勉強しに行かせていただいたので。
せっかくなら、『大阪で得た経験を活かした方がいいよな』っていう想いはありますよね。
よくあるじゃないですか、ルーティンで色々な部署をまわされるような人事。

観光系の部署に出向した後、福祉の部署に配属される的なやつですよね。
観光のノウハウをめっちゃ蓄えて帰ってきたのに、全然発揮する場がないみたいな悩み、よく聴きますもん。

もったいないですよね。
まぁ3~4年で異動するのが、我々の公務員業界の常識になっちゃってますけど。笑

たしかに。笑
希望したら、同じ部署に長く居れたりするんですか?

必ずしも希望が叶うわけじゃないですけど、最近は人事希望の調査もあったりしますよね。
職員の希望だったり能力に応じて人事異動が決定するんだと思いますけど、以前よりは希望が反映されやすくなってきたんじゃないかなと思います。
商工観光PR課について

ちなみに下麦さんの所属する商工観光PR課の観光PR係って、何人体制の部署なんですか?

係長まで含めて4人です。

下麦さんは7年目だということでしたけど、他のメンバーは入れ替わるんですよね?

もちろん。
僕意外、全員変わってますよ。
課長も3人変わりましたし。笑

まぁそうなりますよね。笑
商工観光PR課の仕事って、コロナの影響をモロに受けてそうですけど、どんな働き方をされてるんですか?

内勤が多いかなぁ。
コロナ前に比べたら、外に出る機会は減ったと思います。
出張も無くなったし、極端に言うと、イベント自体が無いから。

そうなんですよ。
僕は所属がグリーンツーリズム推進課なんですけど、うちの課もそんな感じです。

ですよね。
例えば『物産展のイベント』があったとして。
イベント前に出店業者さんの所に行って内容を詰めたり、イベント事態の準備をしたり。
そういう目的で外に出る機会が多かったんですけど、一切なくなってしまったので。

なるほどなぁ。

下麦大志のパーソナリティ
ルーツ

そもそも下麦さんって、さつま町の出身ですっけ?

ですよ!
宮之城町(現 さつま町宮之城地区)の出身で。
高校は川内高校に通ってましたけど。

大学も鹿児島ですか?

いえ、私立の千葉商科大学に行きましたね。
大学を卒業した後に鹿児島へ戻ってきて、宮之城町役場で働き始めました。

大学で県外へ出られたんですね!

高校生の時『とにかく県外に出たい!』って言う、わけのわからない思いを抱いていたので。笑

鹿児島県民あるあるですよね。笑

そうなんですよ。笑
なので、県外の大学を受験したんですけど、落ちまくったんです。
「浪人したいんだけど。。」って両親に持ち掛けたら、父親から「ダメよ!」って言われて。。

なるほど。笑

1校だけ千葉商科大学に合格してたので、「そこに行け!」みたいな感じになって。
「えー。。」と思いながらも通い始め、結果的になんとか卒業しました。笑
就職氷河期のど真ん中

僕が就職活動をしてた時期って、就職氷河期のど真ん中だったんです。
さらに言うと、当時の宮之城町役場は合併も控えてたから、僕の同期は2人しかいないんですよ。

すご!
めちゃくちゃ狭き門じゃないですか!

良く合格したなぁって、自分でも思ってます。笑

笑笑
宮之城町役場以外にも、公務員試験受けたんですか?

受けてましたね。
『公務員になりたい』って思っていたので。

公務員になりたいって思ってたんですね!

ですねぇ。
そもそも宮之城町役場に関しては、採用が無いんじゃないかなって思ってたんです。
でも、かあちゃんから「採用あるらしいよ!」って連絡がきて。
役場の願書も、かあちゃんから送られてきましたもん。笑

かあちゃんの熱量が高い。笑

「とりあえず書いて出せ!」と言われたので、「わかった」って言って。笑

笑笑


亡くなったばあちゃんが、役場に就職することをめちゃくちゃ喜んでくれたのを覚えています。

だと思いますよ。
我が家も、両親以上に祖母が喜んでくれた記憶がありますもん。

僕も下麦さんと同じぐらいの年齢だと思いますけど、僕らの就職の時って、本当に氷河期でしたよね。
僕は奄美の出身なんですけど、それこそ地元の町役場に入ろうとしたら、ちょうど採用が無くて。

そうなんですか⁉

なので、仕方なく今鹿児島市役所で働いてるっていう。。

仕方なく。笑
奄美のどちらなんですか?

徳之島の伊仙町っていう所なんですけど。

おお!
伊仙町なんですね!!

それこそ、当時は数年毎にしか町役場の採用が無くって。
自分の年はちょうど採用が無かったんですよ。
あーもうだめだねーって思って。

笑笑

小さい頃の記憶

『公務員になりたかった』と先ほどおっしゃっていましたけど、いつ頃から公務員という職業を意識し始めました?

中学生ぐらいの頃からなんとなく意識してた気がします。
というか、うちは実家が自営業なんですよ。
弁当とか惣菜とか作ってて。


小さい頃、友達が休みの日にあちこち家族と出かけてるのに、我が家は休みの日でも注文が入ると両親は仕事をするから、どこも連れて行ってもらえなくて。
「なんでうちだけ遊びに連れて行ってもらえないの?」って思ってたんですよ。

(うんうん)

大人になったらね、「仕事だからしょーがねぇよ」って思うけど、子どもながらに「なんか嫌だなぁ」って感じてて。
それだったら、決まった休みがあるサラリーマンになるかなぁって思ったんですよ。

へぇ!

そこから、中学生ぐらいになって、公務員っていう仕事の存在を認識し始めるんです。
街のために、地域のために、働ける仕事があるんだって。
そんな風に働けるって、なんか面白そうだなぁ、役場とか入れたらなぁって、漠然と思い始めましたね。

働きながらもう一度大学へ

ということは、大学に入る時も公務員になることを前提として学部とか決めたんですか?

ですね。
公務員になるんだったら、文系のこういう学部かなぁみたいな感じ。
結局、経済系の学部に行くことになるんですけど、本当は政治を学びたかったんです。
でも、受からなかったので、しょーがないなと思いながら。

なるほど。

ただ、役場に就職してすぐの25歳ぐらいの時、ふと『もう一回大学行ってみようかな』って思い立って。
慶應義塾大学について調べてみたんですよ。

働きながら大学へ⁉

ですです。
調べてみたら、社会人も仕事しながら入学できる通信教育があったので、『ちょっと行ってみようかな』と思って。
大学受験で失敗しまくった法学部政治学科が慶應にはあったことも、挑戦しようと思った要因ですね。

すごい行動力ですね。。

でも、いざ行ってみたら、試験がむちゃくちゃ大変で。。
専門の試験はもちろん、語学の試験がはんぱなく難しかったですね。。

難しそう。。
というか、さつま町役場で働きながら大学に通ってたんですよね?
めちゃくちゃハードだったんじゃないですか?

教科書とかは送ってきてくれて、『自分で時間をつくって、どんどん勉強を進める』っていうスタイルだったんですよ。
このコロナ禍のご時世なら、家時間が増えてるから勉強出来るのかもですけど、当時は若かったから勉強以外にもやりたいことがたくさんあって。。
欲望との闘いでしたね。笑

でしょうよ!笑

最短2年間で卒業できるカリキュラムだったんですけど、勉強が捗らなくて。。
卒業するまで4年間ぐらいかかりましたもん。笑

笑笑
当時って、試験はどんな感じで実施されてたんですか?

1年に2-3回、試験があるんですよ。
会場が指定されてて。
九州だと、1年の間に鹿児島で1回、熊本で1回みたいな感じだったので、別会場の熊本にも試験を受けに行ったりしてましたね。

試験を受けるためだけに熊本まで言ってたの、すごすぎますね…‼

夏場は仕事を2週間ぐらい休んで、東京のスクーリングに行ったり。
役場としても、年休じゃなくて、大学に行くための特別休暇みたいなのを認めてくれたので、それを使わせてもらってましたね。
つくづくラッキーだった

なるほどなぁ。
慶応での4年間で、ずっと学びたかった政治について、じっくり学べましたか?

ですね。
卒論指導は、法学部教授でいらした元鳥取県知事の片山善博先生にお願いし、面倒を見てもらいました。

おお!

しかも、指導期間中の1年半の間に片山先生が総務大臣に就任されて、その間もお時間を作っていただきご指導してくださいました。

すごい状況!
めっちゃ貴重な機会ですね…‼

なんですよ。
ちなみに、卒論のタイトルが『税から見る自治への可能性〜課税自主権の行使に向けて〜』でした。
自治体が新しい税金の制度をつくるためには、国(総務省)と協議が必要なんですよね。

なるほど。

卒論を書いている田舎の役場職員の指導教授が、自治体と協議する側の総務省のトップだったというのは、後から考えると、普通は有り得ないことで。
自分がつくづくラッキーだったなと思います。
卒論指導を通して、片山先生との話はめちゃくちゃ面白かったですし。
税務課という仕事

大学時代のお話を色々と伺いましたが、新卒で公務員になってみて、思い描いてた公務員像と現実の違いは感じました?

僕は技術職じゃなくて一般事務職なので、役場の中には本当にいろんな仕事があるんだなぁって感じましたね。

たしかに。
暮らす上で直接関わらない部署って、役場の中にたくさんありますもんね。

そうなんですよ。
新規採用で最初に配属されたのが税務課だったんです。
自治体にとって税金って、一番要の部署じゃないですか?


たしかに。

役場の根幹をなす税務課を最初に経験できたっていうのは、自分の中では大きかったなぁって思ってます。
先輩方とも、よく話をするんですよ。
『若いうちに税の部署は経験してた方がいいよね』って。
税金=自治体の血液

なぜ若いうちに経験してた方が良いと感じるんでしょう?

自治体は『税金』があるからこそ、様々な事業や施策が実施できているわけで、いわば自治体の血液的なものかなと思います。
自主財源としての市町村税もあり、国からいただく交付税もあり、様々な血がありますね。

なるほど。

若いうちにその分野に触れることができ、なおかつ、しっかり勉強できると、自分自身の『節税』にもつながるところは、大切な部分だと思うんですよ。

めっちゃ共感します…‼
僕自身、ここ数ヶ月で税金のことがうっすら理解できるようになり、お金に対する価値観がかなり変わってきましたもん。
今まで『知らなかったこと』でめちゃくちゃ損してきたなって。。

そうなんですよ!
税申告の際、事業をされている住民の方に、
「脱税はダメですが、節税はいいと思いますよ。きちんと経費となる部分の領収書をとっておいてくださいね。それが節税の一歩です!」
と、お話してました。

ほんとにそうですよね。

『税』は市町村事業の利用料やサービスを受ける際の算定基礎になるので、自治体職員であればどこの部署でも関わってきますよね。
そのあたりも勉強していて損はないかと思います。
ただ、私が異動してから税制改正が多く、もう分からない。。涙

細かいところはともかく、大まかな概要を知だけでも、得られるものは多いと思います。
自分の生活に直結してるから、学んでて面白いんですよね。

普通のサラリーマンは年末調整くらいですもんね。
最近はふるさと納税をして、節税される方も多いですよ。
まとめー前編ー
周りの友達に比べて、休みの日にあまり遊んでもらえなかった
下麦さんが公務員を目指し始めたルーツとして、『実家が自営業で休みの日にあまり遊んでもらえなかったこと』を挙げていたのが印象的で。
『惣菜や仕出しのお店を営む両親の元で育った』というルーツがあるから、民間や自営業者の方の想いが分かるんだろうし、そんな下麦さんが町のために働きたいと公務員になり、民間の仲間たちと一緒に地元を盛り上げようと活動している。
うまく言葉で表せないけど、点と点が線になって、時代が繋がってるんだなって感じます。
ということで、 前編では、コロナ禍での働き方や、下麦さんのルーツについて、お話を伺いました。
中編では、公務員としてやってきたこと&やっていること(移住ドラフト会議やオンライン交流会)について、お話を伺います。
では、また次回お会いしましょう!


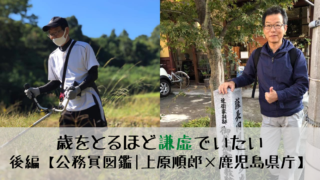

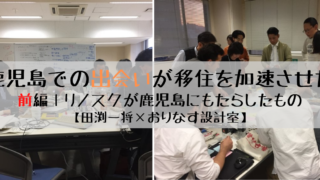
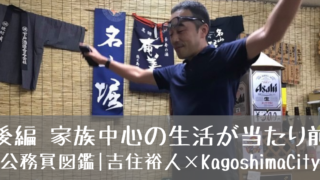




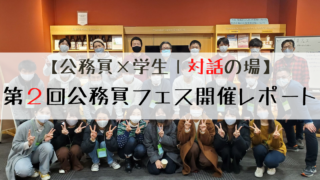
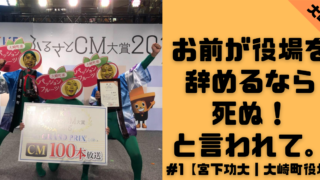

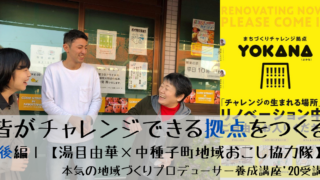
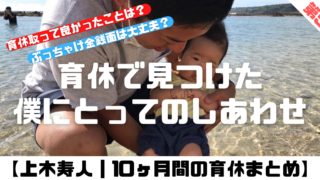
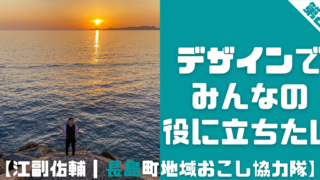
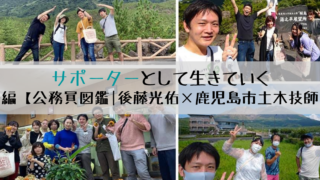
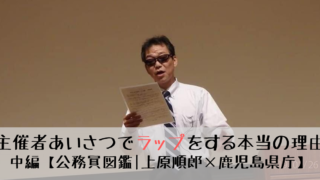
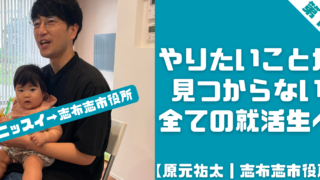



コメント